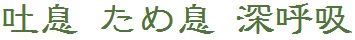実験科学「超」整理法
野口悠紀雄氏著、「超」整理法、正編、及び、時間編は、社会に大きなインパ クトを与えました。それは、誰にも関係があり、誰にでも実践できる、という点 において、大きく評価されたからです。その応用として、主に実験科学に携わる 実験室における空間と時間の管理方法について考えてゆきたいと思います。当然 実験研究そのものは科学的に進められていますが、実験室の管理やデスクワーク などは必ずしも科学的に行われているとは言い難い実験室や場面に遭遇すること があります。決して私が、すばらしい方法を考え出して管理しているわけではあ りません。ただ、困ってあれこれ思索し、いろんな分野における国内外の研究者 の取り組みと研究室を見せて頂いて考えた上で、思いついたことなどを少しずつ 提案します。
CONTENTS
1.デスク周辺の物理的機能性2.共同空間利用のルール
3.実験室の機能性
4.実験空間の拡大方法
5.研究計画の準備
6.プロジェクトの把握
7.発想法あれこれ
8.実験ノートの活用
9.コンピュータのファイル名
10.スケジュールと雑用
11.研究室レベルでの省資源
12.実験中の時間管理
1.デスク周辺の物理的機能性
まず、現時点でのあなたのデスクの上とその周辺の点検から始めましょう。 実際に行動した上で次の設問に答えて下さい。 a. デスクの上で、A4ノートを広げられる、すなわちA3用紙以上のスペ ースがない。 b. 思いついたことをメモ用紙に書き始めるのに2秒以上かかる。 c. よく使う辞書・辞典類を引き始めるのに5秒以上かかる。 d. ある日の日付、例えばちょうど3ヶ月前の任意の日の実験ノートを開く のに10秒以上かかる。 e. 最近1年の間に、ある捜し物のために30分以上かかったことがある。 f. デスクの手の届くところに並べた本の中に、最近1ヶ月以内に開いたこ とのないものがある。 g. 電卓、ステイプラー(ホッチキス)、赤ペン、修正液などの小物がすぐ 見つからない、あるいは、すぐ使えない。 h. デスクの上に飲み物・食べ物(菓子類を含む)や、その残骸がある。 以上の設問に対し、Yes が1つでもあるようなら、改善の余地があります。ページのTOPに戻る
2.共同空間利用のルール
実験室を一人で使うことができるような環境にある研究者はまれです。研究 室単位の実験室や、あるいは、共通の実験室を複数で使う場合、機能性を追求 する前に、共同利用について考えなければなりません。 ごく当たり前のことをきちんとします。開けたら閉める、出したら戻す、借 りたら返す、汚したらきれいにする、ゴミが出たら片づける、壊したら修理す る(もし自分でできない場合は修理を依頼する)。そうしたルールを最低限守 らないと共通空間を維持できません。また実験室の一角に自分の実験台などと して割り当てられても、決して自分だけのスペースではありません。そこで何 をしてもよいというものでもどんな管理をしてもよいというものではありませ ん。周りの実験内容や性質を把握した上で、全体の配置を考え、換気などにも 気を配ります。例えば、有機化学合成を行っている実験室に生物実験を持ち込 んだり、またその逆は避けられなければなりません。そうした区分の重要性を 認識します。毒物劇物、塩化物、引火性危険物などを用いる場合には特に注意 する必要があります。実験室や廊下で走るのも危険です。 また、共通品の管理の方法もしっかりしておかなければなりません。特に鍵 などは、所在をはっきりさせ、速やかに保管場所に戻すことを徹底しないと、 不注意な者が一人いるだけで、全員が右往左往し大きな損失となります。精密 機械の保守・管理も同様です。実験機器等のマニュアル類は場所を決めて一括 保管するのがよいでしょう。取り扱い上、頻繁に参照する部分はコピーを取っ て利用します。また、機械類にはそれぞれ保守管理の担当を決め、必要に応じ てログノート(使用記録)を付けましょう。ページのTOPに戻る
3.実験室の機能性
実験室で実験する場合、作業場あることを意識して工夫することで、機能性 が改善されます。例えば学生が、研究室に所属し実験を開始するようになって 与えられた実験台で、個人的に使用する小さい器具・機器でも使い勝手考えな い配置で実験することが多いようです。研究室の先生や諸先輩方の工夫によっ て機能的になっていることが多いのですが、まだ改善の余地がないか見回すと よいでしょう。ひょっとすると以前は性質のやや異なる実験を行っていたかも しれません。頻繁に使う器具や試薬なども全く同じとはいかないでしょう。そ うなると自分の実験に適した配置に試行錯誤の上、改善することが可能になり ます。 デスクワークの場合も同様ですが、よく使うものはできるだけ手の届く範囲 において、すぐ使いやすいようにしておきます。試薬瓶や、見た目は似通って いるが使い分ける機器類などを色の付いたシールやラベルで区別します。色で 区別する有用性は「超」整理法でも述べられているとおりで、特に実験におい ては有効と感じています。また、実験台や機器の間の隙間があれば塞ぎます。 貴重なサンプルなどが落ちたり転がってしまった時に取り出す時間と手間は、 秒分単位で行う必要のある実験中であれば致命的になります。また器具も工夫 しましょう。ちょっとしたアイディアで、手間・時間の節約ができるというこ とを頭の片隅においておけば、何かの拍子に工夫が思いつきます。セレンディ ピティーと呼ばれるものです。 近所の研究室や、知り合いのいる実験室を訪ねる機会があれば、「機能性」 というキーワードを意識して眺めれば何らかのアイディアを得ることができま す。雑然としていても機能的に配置されていることや、整然としているからと いって必ずしも機能的になっていないことなども見えてきます。時には反面教 師となることもあります特に、分野の異なる研究室からは得られるものが多い と思います。これらは実験室の機能性だけのものでなく、研究そのものでもい えることですね。ページのTOPに戻る
4.実験空間の拡大方法
一般に実験台は狭く、手の届く範囲に全ての必要な実験器具や試薬等を配置 することはできません。できるだけ無駄な空間を作らないように最適化し、空 間を節約できるものを探しましょう。また、必要だからといって所狭しと並べ ると、かえって効率が悪くなります。スペースも時間と同様、作る努力をしな ければ、得られません。指の長さや手のひらを広げたときの長さを知っておく と、定規や巻き尺がなくても、ある長さ、高さや広さを推定でき便利です。 事務用品の小物入れや書類箱なども実験台で実験に使うものを整理するのに 有効です。ただ並べるより、積み重ねられるところは立体化するとよいでしょ う。ただここで注意しなければならないのは、危険な積み上げや通路をふさい だりしないようにすることです。書棚、試薬棚などを高く積み重ねるときは、 倒れないように、天井につっかえ棒を入れたり、チェーンや金具などで壁に固 定しましょう。また、空間を最適化すると言っても、大きくて重たいものを高 いところに置くことや、直射日光が当たるところに有機溶媒を配置しないよう な注意も必要です。 実験中においても、ふとアイディアが浮かんだり、しなければならないこと を思い出したりしますから、メモ用紙、ポストイットをすぐ手に届くところに 置いておいた方がよいでしょう。メモには、必ず日付を記し、一時的な試薬調 製のレシピなどについても、保存することをお薦めします。次の機会に再度利 用できたり、実験がうまくいかなかったときに、そのレシピが残っていたら、 誤りがなかったか確認できるからです。メモ用紙は紛失しやすいので、小型ノ ート、あるいはメモ帳を常にポケットに入れておくとよいでしょう。また、ポ ストイットは、直接書き込みができない実験器具やデータシートにラベルする ことにも利用できます。ページのTOPに戻る
5.研究計画の準備
ただ一つのテーマにのみ、そしてそれに対して一面的に取り組むことができる という研究者はほとんど例外なくいません。常にいくつもの異なるプロジェクト を抱えているのが普通です。しかし、それらが理に適った方法で管理されている でしょうか。 では、1日でできる仕事量(実験とデスクワークの両方)のことから考えてみ て下さい。両方の組み合わせで、どれくらいのことができるでしょうか。では、 最近の1週間で、そして、1ヶ月でどれだけのことができたかについても考えて みて下さい。次に、明日1日の内にしなければならないこと、これから先の1週 間、そして1ヶ月でしなければならないことをリストアップしてみましょう。そ れらのしなければならないことを終えるのに実際にどれくらいの時間がかかるか 考える必要があります。さらに、その期間にも予定外の様々な要件が入ってくる に違いありません。入ってくるものの中には、例えば毎年ある決まった時期に定 期的に行われる学会行事や組織の行事など、予測できるものもあります。それら の要件があってもなお、予定はこなさなくてはなりません。締め切りがあるもの については、特に忘れないようにし、必ず守りましょう。1ヶ月まで考えたら、 次は、3ヶ月、半年、1年の期間で考えます。そのスケジュールは、「超」整理 法・時間編で提案されているような長期(半年から1年)を一目で把握できるよ うなスケジュール表を作るとよいでしょう。私の場合は、システム手帳の片面3 ヶ月(見開きで6ヶ月)の予定表を用いています。締め切りが特に無いものにつ いても、進める時期と達成のめどを立て、早めに実行します。 長期のプロジェクトではこれが重要で、途中で進路変更を余儀なくされる場合 も全体計画との整合性を検討し、達成の内容・時期を改めます。また、派生的に 得られた興味ある結果が得られたけれども、それがプロジェクトから離れた内容 である場合、どう取り扱うか、よく考えます。サイドプロジェクトとして取り組 む余裕があればよいのですが、そうでなければ一旦そのアイディアを寝かしてお きます。おもしろいからといって、メインプロジェクトを放っておいてはいけま せん。ページのTOPに戻る
6.プロジェクトの把握
各研究プロジェクトに関して、それぞれの進捗の段階を把握していなければ、 計画や予定は立てられません。次の4段階に分類した上で、その一覧をデスクか 実験室のよく見えるところに貼っておくか、TO DO リストと一緒に管理します。 1)getting started まず始める 2)in progress 進行中 3)some experiments remained 2、3やり残しがある 4)to be written 論文にまとめる 数あるアイディアの中で実験に移せそうなものを 1)getting started にリ ストアップします。関連する研究の文献を調べ、どのようなアプローチがユニー クで効果的かをよく考えます。少しでも余力ができた時などに、とにかく始めま しょう。 次に、実際に実験を開始し、ある程度まとまったテーマになりそうなものが 2)in progressです。この段階のものには、時間と労力を十分に配分します。 この2)の段階のプロジェクトの中でも、優先順位を考えないといけません。も ちろんメインのテーマが当然優先されるのでしょうが、常に優先されるとは限り ません。時間支配の優先順位の一時的入れ替わりもありますから、リストを貼っ ておき、必要に応じて順位を入れ替え、一目で分かるようにしておきましょう。 そして、あるテーマに関して目鼻が立ち、メインの部分は終わったが、2、3 の実験が残っているものが 3)some experiments remainedです。早いうちに 仕上げることを意識しておきます。発表の形態に合わせて、それまでに得られた データを表やグラフにまとめ、一つのまとまった研究とするのに、あとどのよう なデータが必要かを書き出しておく。 データがそろったと考えたら、論文を書きます[4)to be written]。 そろ ったと考える判断は易しくありません。他の研究グループと競合している時は焦 るものですが、冷静に考えてから投稿します。競合が無いと今度は逆に欲が出て 総合的に研究が終わるまでと論文発表を先に延ばしがちになります。また時間が 経つと、に行った研究が陳腐に感じ始め、論文を書く気持ちが薄れる場合もあり ます。そうならないうちに、論文として書き下ろす努力をします。論文の書き方 については、「理科系の作文技術」木下是雄(中公新書)、「化学のレポートと 論文の書き方」(科学同人)等、優れた成書がありますからご参照下さい。ページのTOPに戻る
7.発想法あれこれ
発想法、アイディア創出に関しての著述はたくさんあります。それは、アイ ディアを得ることがどれだけ重要で、かつ困難かということを意味します。そ うした本を読むことで、すぐ発想できるようになることを期待してはいけませ ん。それぞれの著者がそれぞれの苦悩の中から考え出した方法なので、それら をよく検討した上で、自分なりの方法を試行錯誤してゆくほか無いでしょう。 何の準備もなく、アイディアを得ようと言うのは虫が良すぎます。まず何より も、問題を意識し考える心構えを持つことです。 アイディアは日付とともに、カードやメモに書き、ひとまとめにし、そして できればさらにコンピュータファイルにします。とりあえず、研究に関係なく ても、何でも思いついたことは記録しておきます。そして、折に触れ、眺め、 考えることで熟成されていきます。また、アイディアを生む環境づくりにも気 を配り、集中したいときは、電話などで妨害されないようにしなければなりま せん。発案の場は、昔の三上として有名な馬上、厠上、枕上は、現在では乗り 物の中、トイレ、布団の中に相当すると考えられ、いずれも重要な場です。少 なくとも、そこで思いついたことを逃がさないようにメモ用紙をおいておく必 要があります。加えて、風呂の中も集中できる恵まれた場で、紙と鉛筆があれ ば少々濡れていても、キーワードくらいは記録できます。アイディアの逃げ足 は速く、一旦逃げたアイディアを思い出すストレスは大きいものです。 いかに違う観点から焦点を当てるかを考え、他分野の研究者との交流を大切 にして、違うものの見方、考え方を学びます。折に触れ、辞典や事典類を読み 周辺領域の情報をアップデイトしましょう。オンラインでの最新の文献検索を 行うことで、集め漏らしていた情報をキャッチします。検索を行うキーワード も、少し表現や単語を言い換えることで、別の論文が引っかかってくることも あるので、最初のうちは試行錯誤が必要かもしれません。 普段から問題点を頭の片隅においておき、アイディアが出てきたときに確実 に捉えるための準備をしておくことが大事です。ページのTOPに戻る
8.実験ノートの活用
実験科学で行ったことは実験ノートに記録を取らなければなりません。化学 同人の「論文の書き方」などの中で具体的記載の例も取り上げられています。 記録能力も研究者には重要です。実験中に使用するメモ帳、方法・結果などを 記録・保管する実験ノート、アイディアやセミナーなど行事の記録日誌の3つ に大きく分かれます。 実験中に使うメモは、不必要になったコピーの裏が最適です。デスク、電話 台、実験台、コンピュータ机、測定機器のように、メモや思いついたアイディ アなどをすぐに書く必要がありそうな場所にはあらかじめ置いておくとよいで しょう。しかし実験内容に関することはできるだけ、糸で綴じたノート型のメ モ帳に書くようにし、実験中は常に持ち歩きます。細かい実験条件や試薬調製 のレシピといった実際に用いたものを日時とともに残しておけば、後になって 問題が生じた時の確認や、同じ実験を繰り返す時に再計算の必要のない効率的 な参照が可能となります。そのためにも、バラバラの紙では失われ易いので、 しっかりしたメモ帳を用いるのが好ましいのです。もし、メモ用紙を使った場 合は、それをメモ帳に張るとよいでしょう。 さて、最も重要な実験ノートについて考えましょう。できれば実験ノートの 電子化をおすすめします。実験ノートとは別に、実験の方法や結果をコンピュ ータのテキストファイルで蓄積・保存することは、自分の実験のデータベース を構築することと同じことです。テキストファイルなら、キーワードで短時間 のうちに検索することが可能になります。また、似たような実験や繰り返し実 験では、以前に作成した部分をコピー/ペーストして雛形とし、異なる部分だ け手を入れることで簡単に編集できます。また、ファイルをバックアップする のは簡単ですから、場所を取ることもなく2つ3つと別の所で保管することも 容易です。もちろん、データの管理には気をつけましょう。 アイディアやセミナーなどの記録もたいへん重要です。講演会やセミナー、 ミーティングの会場ではノートということになりますが、あとで差替えられる ルーズリーフが便利です。取ったメモは、その日のうちにもう一度考察し直し ふるいにかけ、重要と判断したものは別に書き足して保存します。このノート は将来いろんなアイディアを生むことになるでしょう。ページのTOPに戻る
9.コンピュータのファイル名
実験を計画・進行し、データを得、結果を論文や報告の形でまとめていく過 程や予算申請で、また、実験に付随する事務処理などにおいて、コンピュータ で作業することは欠かせません。作業とともにファイルが発生し続け、コンピ ュータのハードディスクなどの記憶装置の中身は雑然としてきます。その整理 方法について考えてみましょう。 まず、ファイル名の長さです。マッキントッシュやウィンドウズ95では、 ファイル名の文字数に特に制限はありません。しかし、MS-DOSレベルで は、ファイル名8文字(半角英数字で8文字、全角文字では4文字)に、ピリ オドを挟んで拡張子3文字というのが一般的です。最近では、機種やOSの異 なるコンピュータ間でのファイルの互換性もある程度出てきました。ファイル を転送したり整理したりするユーティリティーでは、まだMS-DOSのプロ グラムも多いので、8文字以内にしておいた方が今のところは好ましいといえ ましょう。また、アプリケーションが拡張子を使うものが多いので、個人で拡 張子を設定する場合は、よく検討する必要があります。ファイル名の文字数制 限がない場合でも、マウスでクリックするだけでなくキーボード入力が必要に なる場合もありますから、長いファイル名は避けた方がよいでしょう。 次にファイル名。ファイルの数が膨れ上がってきたり、時間とともにファイ ル名とファイルの中身が結びつかなくなってくることがあります。したがって 少なくとも自分自身のファイル名はある程度の規則性を与えましょう。 [プロジェクト関連ファイル] PPPPYYTT.txt あるいは、 PPYYTTEE.txt PPPP, PP : プロジェクト名、YY : 年、TT : 種類、EE : ヴァージョンなど 例、研A98計.txt(研究A:98年度計画) 化学97要.txt(日本化学会97年度講演要旨) [測定・分析関連ファイル] YYMDDNNT.xxx YY : 年、M : 月 (1-9, X-Z[10-12])、DD : 日、NN : その日の通し番号、 T : 種類など、xxx : 機器やアプリケーションが与える拡張子 例、97X2405W.xxx、 98303B4L.xxx [通信文ファイル] NNNNNNYY.txt NN : 宛先の名前、YY : 年、 同じ宛先は年毎にまとめ、書き足していくとあれもこれも開かなくてよい 例、大阪研98.txt、 DFB98.txt (David F. Brown 宛98年) ここで注意したいのは、以前に作った例えばAAA.docというファイルを手直 しして、AAA-new.docとか AAA-r.doc(-r は revised、改訂版)といった 名前を付けてはいけません。さらに手直しする可能性があるので、"new"は "new"でなくなり、revised の revised が出てくるからです。単に通し番 号を付けるか(AAA-02.txt)、手直しした時期を付ける(AAA9803.txt)の がよいでしょう。 あと、個人レベルでの2000年問題があります。98, 99, 00, 01, ... とした場合、ソートすると 00, 01, ..., 98, 99, となりますから、便宜的 に 98, 99, A0(2000), A1(2001), ... とする方法もあります。特別、問題 があるわけではありませんが、一応心の準備をしておきましょう。ページのTOPに戻る
10.スケジュールと雑用
実験研究そのもののスケジューリングはもちろん重要ですが、実験以外のスケ ジュールの管理もしっかり行わなければなりません。適切でなかった場合、実験 にも大きく影響を及ぼします。 まず、1年の中の定期的な学会や会議などの行事を予定します。過去2,3年 のスケジュール表を活用することで、毎年同じ時期にある行事が分かります。研 究費の申請締切や学会発表では、さかのぼった計画が必要になります。次に、定 期的ではないが今後予定されている行事を書き出します。研究会の幹事や、当番 制の仕事など数年に1度引き受けるようなものもあります。さらに、論文審査な ど突然、期限付きの仕事も入ってきます。このようなものはその都度、予定に入 れるしかありません。それらはスケジュール表に書くだけでなく、TO DO リスト に期日とともに書き加えます。ホワイトボードを利用する方法もありますが、持 ち運べないので手帳にポストイット貼る方法が有効です。色で、カテゴリや重要 度、あるいは緊急度を区別できます。終わればはがすことでリストからはずせま す。ただし、重要事項は決済日時を書いてしばらくの間、保存するのがよいでし ょう。単にリストからはずした場合、ふと「あの件の締切は明日だったはず」な どと思い出して驚くことがあるからです。締切が迫っていない事柄でも、時間が あるときに片付けます。 重要な要件はもちろんのこと、重要度が低いものでも、締切や時間は厳守しな ければなりません。共同社会の中で、時間は決して自分だけのものではありませ ん。自分の時間を不届き者に奪われない様にするだけでなく、予定管理のまずさ から人の時間を奪わないことが必要です。電話は極力避け、電子メール・FAX などそれぞれの特長を生かした利用を考えます。「超」整理法・時間編をご参照 下さい。居室や実験室の電話を留守番電話にしておけば、電話がかかってきたと き、録音中のメッセージを聞いて、出る・出ないを判断することも可能となりま す。保険・貯蓄・投資などのセールス(電話と訪問の両方の場合がある)や、実 験機器に関するセールスへの対処法もあらかじめ考えておけば、邪魔される程度 も小さくなります。アイディアを練ったり、研究費の申請、論文執筆、学会発表 準備などで、電話などの邪魔のない、まとまった集中できる時間が必要なときの ため、可能なら隠れ場を持っておくと役に立ちます。それが不可能なら、電話か ら遠いところで耳栓をしておきましょう。 誰しも組織に属している限り、雑用から開放されることはありません。大学や 研究所、企業など所属機関内部での諸々の委員会・会議、その他書類作成、外部 では学会や研究会などの運営事務に関する仕事など数かぞえ上げればきりがあり ません。ただ不平をこぼすだけでは何の解決にもならないので、うまく付き合い こなすほかないのです。 まず、何よりもむやみに引き受けないことです。といっても、一切を拒否する ことはできませんから、必要とする時間と労力をよく検討し、できるだけ公平に なるような方法を相談した上で負担しましょう。関係する全員がこれで公平と納 得することを望むのは不可能なので、大きく不均衡にならない程度で妥協しない と、今度はその相談の時間もかさみます。引き受けるべき時は引き受け、そのと きはちゃんとやります。しかし、雑用はあくまで雑用であり、それに振り回され てはいけません。雑用に関しては、完璧なことを目指さず、拙速であることを心 がけると精神的な負担も大きくなりません。ページのTOPに戻る
11.研究室レベルでの省資源
化石エネルギーの消費は地球温暖化を、紙の消費は森林伐採による砂漠化を招 きます。それらの消費は、第1次産業だけでなく、他の産業や個人の生活におい ても積もり積もれば莫大なものとなります。省資源に努めるのは一地球人として の責任だといえましょう。では、研究活動における省資源についても考えてみま しょう。 大学でも、企業でも、研究室を抱える部署の電力消費は相当なものです。節電 に努めることは、化石エネルギーの枯渇と地球温暖化の両者の抑制に貢献するも のです。また、光熱費も研究費から出るわけですから、光熱費をできるだけ抑え る努力すれば、実質の研究に使える部分が増えるわけです。電力を、研究に不可 欠なものとそうでないものにきちんと区別します。無人の実験室の電灯を消し、 必要のない機器類はつけっぱなしにしない。冷却機能付きの装置は必要な場合を 除いて冷却機能を切り、ふたを開けたままにしない。この場合、冷却装置を使い スイッチを切った後でも、ふたを閉めないと中に結露してサビや故障の原因にな るので注意します。 水も同様です。水不足になりやすい地域は特に、それ以外のところでも、節水 に心がけます。脱イオン水や純水も大事に使います。こちらは、精製装置を出る と時間とともに質(純度)が低下しますから、必要以上に取り置きをせず、必要 な量を必要なときに用意します。そうすることで精製装置の運転にかかる電力と 脱塩カートリッジの消耗が抑えられるからです。 紙資源に関しては、実験研究室でも一般のオフィスでもそれほど違いはありま せん。余分なコピーは取らない、無駄なプリントアウトはしない。コピーも可能 なかぎり、両面コピーとします。文書を保存する際、かさばりと重さが半分にな るという利点もあります。コピーやプリント用紙も、リサイクルペーパーを使い ましょう。両面印刷し不要になった紙は、リサイクルに回します。片面だけ印刷 し不要になった場合は、しわや折れ・撚れ、ホッチキスで止めた跡のなければ、 プリンタのテストプリントなどに使えます。しわや折れなどがあると用紙が詰ま って、手間も暇もかかるので使わないようにします。カセットで給紙するタイプ のプリンタなら、カセットの一つをそのテストプリント用の裏紙にセットするの も一案です。しわや折れのある紙は、上質のメモ用紙となります。半分や4半分 に切断したものもたいへん重宝します。 省資源には、実はもっともっと基本的なことが有効なのです。濡らしたり汚し たりしたときはすぐ拭き取る、使ったものはすぐ片付ける、使わない機器類には カバーを掛ける、といったことです。劣化や故障を防ぎ、長く使うことが省資源 につながります。液体をこぼした時、その液体が酸やアルカリ溶液など腐食性、 あるいは、無機塩などを含んでいてサビを招きやすい場合がほとんどですから、 気をつけなければなりません。液体だけでなく粉末のものでも、こぼしたらすぐ こまめに掃除します。特に天秤は、汚れやサビなどで不正確になると、実験結果 にも影響が出るので、周辺も含め、きれいに保つ必要があります。 もちろん実験室では、いかにして研究を効率よくスムーズに行うか、が最も重 要なことです。しかし、それを妨げない範囲で、省資源、省エネルギーを行うこ とは可能です。ちょっとした気配りと心がけさえあれば、研究費の無駄を抑える と同時に、地球規模での環境破壊にブレーキをかけることができるのです。ページのTOPに戻る
12.実験中の時間管理
デスクワークと同様に、実験中の時間の管理もたいへん重要です。特に、数 分の待ち時間などの細切れの時間が発生する実験では、ただボーッと待ってい ると、その時間の累積も馬鹿にはなりません。考察を加えてみましょう。 まず注意したいのは、待ち時間を生かそうとして、本来の実験の方を失敗し ないようにすることです。そのためには、タイマーの利用は欠かせません。そ の音にも注意しましょう。実験室にある機器類のアラームと異なるもの、同じ 実験室で仕事をしているもの同士は混乱しないように区別できる音のものを使 用します。そして、タイマーをスタートしたら実験台やデスクに置かず、常に 身に着けておくことが大切です。時間が来て鳴っても、スタートした本人にし か意味をなしません。 では、細切れの死んだ時間を有効に使うにはどういう方法があるのでしょう か。①待ち時間が終わった後の実験手順を確認する、さらにそれ以降の実験に ついても頭に入れておく、②TO DO リストの確認をする、③緩衝液や調製試薬 など常備・ストックしているものの残量を確認し、少ない場合は TO DO リス トに加えておく、④得られたデータを解析する、⑤文献や参考資料を読む(但 し、過度に集中してはいけない)、⑥直接、実験には関係しない自分のための (例えば外国語など)勉強をする、⑦火事や地震といった非常時を想定してど う行動するかを考えておく、⑧実験器具のカタログを眺める、などが適当と考 えられます。この半端な時間にコンピュータに向かうのは、メールの確認を含 め、極力避けた方がよいでしょう。 細切れの時間を利用するには、移動にかかる時間を秒単位で知っておくと便 利です。実験台からデスクまで、電話まで、トイレ往復、別の実験室や会議室 などに行くのにかかる時間を予め計っておきましょう。待ち時間のうちにトイ レに行って来られるか、何時までに実験を片付ければ会議に間に合うか、正確 に把握することができます。 実験の種類によっては、待ち時間が長いものもあります。その場合、いくつ かの実験を並行して行うこともできます。ただし、その待ち時間が最も長い実 験を優先して計画しましょう。また、1時間反応させた後に10分間かかる測 定をする様な実験を繰り返す場合は、時間差を付けてスタートし、無駄な時間 が発生しないような工夫も有効です。(下図参照) 0:00 :10 :20 :30 :40 :50 1:00 :10 :20 :30 :40 :50 2:00 /------------------------------/***** ↑ ↑[測定] スタート ストップ /------------------------------/***** ↑ ↑[測定] スタート ストップ /------------------------------/***** ↑ ↑[測定] スタート ストップ 一日の時間の流れにも気を配ると効率も上がります。頭脳労働と肉体労働 (実験)との配分を考えるのです。集中力を必要とする仕事は連続しない方が 好ましいでしょう。実際にはそんなことをいっていられませんが、可能な範囲 で、気分を切り替えられる様な計画を立てましょう。実験にしても、デスクワ ークにしても、ペースに乗り始めたら、中断するのはもったいありません。同 様に、気分を切り替えるには短時間で行いましょう。頭もエンジンと同じよう に快調に動き始めるのに少し時間がかかりますから、休憩も長くならないよう にした方がよいでしょう。 最後に、次の日の予定(会議や面会など)を確認し、それに合わせた実験の 計画を立て、ホワイトボードなどに書いてから帰ることを習慣づけます。ページのTOPに戻る